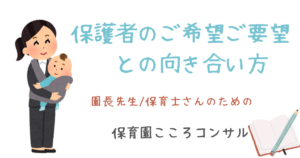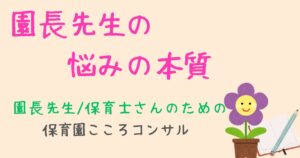保育園という職場での人間関係:基本のキ|ベテラン保育士さんと新人保育士さん
保育園。子どもたちの安心安全を見守る保育士さんのお仕事は、チームワークが命。そのため、互いの信頼、責任、連携がとても大きな意味を持ってきます。
同じ職責を果たすグループメンバー同士。子ども見る視点での、スタッフ同士の信頼があれば、とってもスムーズでストレスレス。その分、同じ仕事内容でも余力が生じ、それを子どもへのさらなる深い理解へと、向けることができますよね。
では、そういった人間関係の困りごと、問題の原因の中から、
今日は特に「ベテラン保育士」さんと「新人保育士」さんの間で生じがちな溝について、
その一端を取り上げてみることにします。

期待と苛立ち
人間関係のちぐはぐは、「期待」と関係することが多いです。
「期待」は、相手に ”こうあってほしい” とか ”これが出来て当然なのに” と思う氣持ちのことです。
では、どうして ”こうあってほしい” とか ”これが出来て当然なのに” と思うのでしょうか?
「期待」は、比較によって生ずることがほとんどです。
では、誰との比較かと言いますと、
主に
「目の前の相手と属性や年齢などが近く、あなたが過去に接したことがある誰か」
あるいは
「目の前の相手と属性や年齢などが近かったとき(過去)の、自分自身」(または、「目の前の相手と属性や年齢などが近くなったとき(未来)の自分自身」)です。
今回は、案外やっかいな後者「(過去や未来の)自分との比較」について
取り上げてみます。
思い出そう:過去の自分の至らなかった点|想像しよう:未来の自分の至らないかもしれない点
こうしてほしい/どうしてあれができないの?/なぜこうしてくれないの?等の判断の基準として、
過去の自分自身(似たような立場や年齢だったときの自分)、
あるいは、未来の自分自身(同じ年頃くらいになった自分)と
その人を比較してしまうことがよくあります。
認知のカラクリ
ここで、人の認知のカラクリです。
過去も未来も「自分中心に美化」されます。
まぁ、それでこそ、たくましく生き抜いてきた私たちヒトという生き物なので、
それはそれでいいんです。
ただ、その基準が、目の前の相手をジャッジする物差しになってしまい、
イライラしたりこじれてしまう場合も、あるかもしれません。
例えば、
ベテラン保育士さんは、ご自身が新人だったときの氣持ちや視点をあまりよく覚えていないかもしれません。
もしかすると、「あの頃は辛かったけど、よく頑張ったなぁ私。それに比べて、、」とか、ふと思ってしまうこともあるかもしれません。場合によっては、これまでに出会った「すごく良くできる後輩や知り合い」が「後輩の基準」になっていたりすることもあるかもしれません。
新人保育士さんは、ご自身がベテランになったとき見えてくるものや、そうなったときの氣持ちを想像するのは難しいかもしれません。
もしかすると、「今の自分がこれくらいなら、○年後にはこういう風になれている!」というふうに、思うこともあるかもしれません。場合によっては、「とても尊敬できる先輩や知り合い」がいて、それが「先輩の基準」になっていたりすることもあるかもしれません。
繰り返しますが、それが人間なので、それでこそ前向きに希望をもって生きていけるので、
その意味ではいいことです。
でも、
まずはそれらの基準を取り払い、
目の前の相手を知ることからがスタート、と考えてみてもいいかもしれませんね。

年を重ねると臆病になる
これは新人さんにお伝えしたいことでもありますが、
一般的に人は、年を重ねる毎に、変化を嫌うようになります。臆病になりがちになります。
それは、守る人や場面、ことやものが増えるだけでなく、
体の衰えを感じるとさらに
変化を怖がる、嫌がる、受け付けなくなる場合もあると思います。生身の命ですから。
そう言った一般論を理解しておきつつも、諦めなくて大丈夫。
ベテランさんも、少しずつそれらの恐怖を乗り越えてバージョンアップしていけますし、
それは自信となり、喜びとなるのです。
そういう姿勢から、学ばせていただくこともあるかもしれませんね。
さらに、年を重ねること、後輩ができる、ということは、責任だけでなく恐怖も伴うことなのです。
それをほんの少し、頭の隅に置いていただくのが1番いいかなと思います。
そのうえで、
敬意を払い、マナーをもつことを大前提として、もちろん言いたいことは我慢せずに伝えていきましょう。
知で得た「べき論」に縛られない
これはベテランさんにお伝えしたいことでもありますが、
ここ10年、20年で、行きかう情報の量はけた違いに多くなりました。
産まれた年代が後になればなるほど、子どもの頃からすでに、
ゆっくりじっくり自分の感覚を味わって、そこで判断するということは
出来にくくなっているかもしれません。
そして、あまりに情報が多いと、人はなるべく省略してポイントだけつかもうとします。
それがある意味自然の姿です。なぜなら、全部まともにとらえていたら、脳が疲れ果てるからです。
この情報化社会の変化に比べて、私たちの身体は数百年前からほどんど変わっていませんから、脳にとってはものすごいストレス社会に生きているのです。
そうすると、何が起こるか。
頭や知的に判断できること、世の中や学問一般でよいと言われていることを受け入れるので精一杯、吟味する余裕も余力もないような子ども時代を送ってきた可能性もあります。
そして今も、世の中には
「子どもにはこう接するべき」という、「べき論」があふれています。
美しい言葉と、理想的なイメージで味付けされているので、疑いようもないと思ってしまうのです。
しかし、保育は現実そのもの。
もしかしたら、新人の保育士さんも、疑うことのなかった「べき論」で懸命に保育を頑張ろうとして、つらくなってしまったり、
思うようにいかずパニックになるかたもいるかもしれません。
そういった背景に思いを馳せつつ、お互いに目の前の子どもにしっかり向き合うことからブレないようにしましょう。
そうすると、新しい何かが見えてくるかもしれません!
一期一会の機会、よりよい保育に向かう同志として、互いに本質への理解を深めていきましょう。

保育園での子どもの理解が、働いているかたの本質的な喜びにもつながりますよう、サポートいたします。